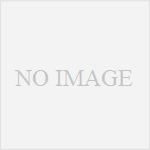さて、石川県の公立高校の入試が終わりました。
とりあえず、理科から分析を書いておこうと思います。
まず、理科は20年以上ぶりに大問構成が変わりました。
今までは、
大問1が小問集(物理化学生物地学から各2問で8問)
大問2~5が物理化学生物地学がそれぞれ1大問。
大問6が融合問題
という感じだったのですが、
大問1が小問集ですが、問題数が
物理化学生物地学で2~4問になり、
13問28点分の配点となりました。
あとは、大問2~5が今までと同じく、
物理化学生物地学から大問1個分ということで。
今までの大問1と大問6が1つに合わさった感じですね。
まぁ、大問6は融合問題とは言え、
近年は、4分野からそれぞれ出題されていたので、
結果小問集みたいになっていたので、
その大問6を大問1に合わせた感じかなと。
さて、各大問ごとには、
大問1は最後の記述以外は簡単目なので、
ここで点数を稼いでほしいところ。
大問2は水溶液。
問1(1)(2)(3)は簡単。
しかし、問2、問3はなかなか難しい。
小松高校レベルなら落ち着いてやれば、
何とかできるが・・・どうだろうか。
大問3は微生物・食物連鎖?
問1はオーソドックスな問題だが、
問2の方はあまり見かけないタイプの実験なので、
戸惑った人も多いかも。
大問4は電力・発熱。
問1問2(3)まではよくあるタイプの問題。
問2(4)は割合を求める問題で計算が苦手な子には鬼門。
問3は考える力が必要な問題だ。
大問5は地層
問1~問4(1)まではやさしい。
問4(2)も問題文が複雑そうに書いてあるだけで、
聞いていることは簡単なのでぜひかけてほしい。
問5はなかなか難しい。
傾きまではわかってもEの掘る深さがなかなか騙されやすい。
ということで、大問2~5は問題の易しい難しいの
グラデーションがしっかりしていて、
非常に良い問題だと思う。
大問1と各大問の簡単目な問題をしっかりと解けば、
そう悪い点数にはなりにくいと思うので、
予想平均点は去年よりちょっとアップの53点。